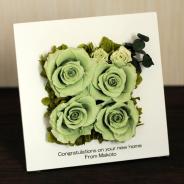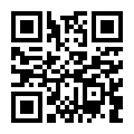街を歩いていても、カフェやレストランにショッピングセンター、さまざまな場所にクリスマスリースが飾ってありますね。
色とりどりで、街をあざやかに演出するクリスマスリース。
眺めているだけでワクワクしますが、その一方で、どうしてこんなに飾ってあるのだろう……と気になりませんか?
いったいなんのために、いつまで飾っているのだろう?なんて、一度気になり始めるとどんどん疑問がわいてきますね。
この記事では、クリスマスリースに関する疑問を、ひとつひとつ解説していきます。
リースを飾る理由だけではなく、意外な活用法や壁に穴をあけずに飾る方法など、いろんなお役立ち情報が満載です。
リースにまつわる疑問を、一気に解決しちゃいましょう!
1章 クリスマスリースを飾る理由

日本でもよく見られるようになったクリスマスリース。
なぜ飾るのか?なんて、キリスト教圏では常識なのかもしれません。
しかしわたしたち日本人には、知らない人の方が多いですよね。
ここでは、クリスマスリースを飾る理由と意味、効果をひとつひとつ見ていきましょう。
1-1、なぜリースを飾るのか?
クリスマスリースには、大きく分けて3つの代表的な意味があるといわれています。
- 魔除け
- 豊作祈願
- 新年の幸福祈願
それでは、ひとつひとつ解説していきましょう。
1-1-1、魔除け
クリスマスリースは、一般的に玄関に飾られることが多いですね。
これは、玄関に飾ることで家の中を守る、という意味があるからなのです。
リースには緑色のきれいな葉っぱがついていることが多いですが、この葉っぱがポイントです。
冬でも青々と葉を茂らせている常緑樹は、古くから強い生命力の象徴とされてきました。
また、葉自体にも殺菌作用や抗菌作用があるため、それらが転じて「災いから家族を守るもの」という意味が生まれたようです。
1-1-2、豊作祈願
リースについている飾りに注目したことはありますか?
松ぼっくりやぶどう、リンゴなどの、果実が飾られているところを見たことはないでしょうか。
麦の穂があしらわれているものもありますよね。
それらの作物を模した飾りには、収穫を祈願するという意味があります。
次の収穫期の豊作を願って飾られているのです。
1-1-3、新年の幸福祈願
日本ではクリスマスが終わるとすぐにお正月の準備を始めますが、キリスト教圏ではクリスマス=当日だけ、ではありません。
年が明けても、まだクリスマスシーズンは続くのです。
ですから、クリスマスリースも年内だけのものではありません。
新しい年の幸せを祈る、日本のしめ縄のような役割も持っているのです。
1-2、クリスマスリースが持つ意味とは?
今度は形状や色、素材に込められた意味を見ていきましょう。
1-2-1、形状の意味
クリスマスリースは、木の枝で作られた輪の形をしています。
輪には「終わりのない」「永遠」などの意味があり、聖書で神を表現する「私はアルファでありオメガである」「初めであり終わりである」などの言葉に通じるため、この形状は重要なのです。
特にクリスマスリースには、「終わりのない永遠の神の愛」という意味が込められています。
神の愛に敬意をこめて作られた形といえるでしょう。
1-2-2、素材の意味
リースにはさまざまな素材が使われていますが、そのひとつひとつに願いが込められています。
・リボン、ベル・・・魔除け
固く結ばれたリボンには、魔除けの意味があります。
日本ではあまり一般的ではありませんが、同じクリスマスの飾りとして「赤いリボンを結んだヤドリギ」がありますね。そちらにも魔除けの意味があります。
ベルは、その音が魔を祓うと考えられてきました。
日本でも、神社でお守りを買うと、よく鈴がついていませんか?
それと同じです。
古今東西、ベルや鈴の音は魔を祓うと考えられてきたのですね。
・モミ、月桂樹などの常緑樹・・・生命力の象徴
最初に述べたとおり、冬でも青々としている常緑樹は、生命力の象徴と考えられてきました。
寒いときは気持ちが落ち込みがちになりますし、なによりキリスト教圏の大半は、日本よりも冬が厳しい土地です。
過去には冬に凍えて亡くなる方も少なくなかったでしょう。
そんな冬に希望と願いを込めて、生命力の強い常緑樹を飾ったのです。
・トゲのあるヒイラギの葉・・・キリストの受難
モミと同じ常緑樹のヒイラギ。こちらもよく、クリスマスリースに使用されています。
ヒイラギの葉は、ギザギザと先がとがっていますね。
それはキリストの受難を表しています。
キリストが被ったのはイバラの冠ですが、ヒイラギの先のとがった葉がその冠を連想させるため、ヒイラギは受難の象徴となったのです。
キリストの受難を飾ることには、宗教的な意味合いがあるようです。
・赤いヒイラギの実・・・キリストの血、太陽の炎
ヒイラギの真っ赤な実は、キリストの血を象徴していると言われています。
また、太陽の炎を表すという説もあります。
民のために血を流したキリストに敬意を払い、恵みをもたらす太陽の炎を願って、神聖なヒイラギの赤い実を飾ることになったのです。
1-2-3、色の意味
近年はさまざまなカラーのクリスマスリースも売られていますが、やはり赤、緑、白、金のリースが定番ですよね。
いわゆるクリスマスカラーと呼ばれる色たちには、やはり意味があるのです。
- 赤・・・キリストの流した血、神の愛
- 緑・・・永遠の命、神の永遠の愛
- 白・・・純潔、罪のけがれのない清らかさ
- 金・・・ベツレヘムの星(キリストの生誕を知らせる星)、高貴さ、希望
白はキリストによって罪がそそがれたこと、金は王として帰ってくるキリスト自身のこと、という意味合いもあります。
あざやかできれいなクリスマスカラーですが、それぞれに宗教的な意味合いがあるのですね。
1-3、クリスマスリースの意外な活用法
クリスマス気分を盛り上げてくれるクリスマスリースですが、せっかく飾っているのですから、インテリア以外にも役立てることができたら素敵だと思いませんか?
クリスマスリースには、インテリア以外にぴったりな使い道があります。
それは、アロマテラピーです。
クリスマスリースには、よくモミの木が使用されています。
モミの木には、先ほど述べたとおり、抗菌・浄化作用があります。
クリスマスツリーを室内に飾る風習は「風邪をひきやすい冬の間、モミの木の浄化作用で空気をきれいに保ち風邪を予防するためだ」という説もあるほどなのです。
また、モミにはアロマオイルもあります。
シベリアモミと呼ばれる海外製のものが多いですが、北海道産のモミ精油も売られています。
モミの精油にも風邪を予防する作用があると言われているので、モミのリースにモミのアロマオイルを数滴つけて室内に飾れば、室内の空気浄化が期待できます。
また、モミの香りにはリラックス効果があるとも言われているので、疲れた気持ちを癒すことができるでしょう。
寝室に小さなリースを置いて、クリスマスを楽しみながら生活に役立ててもいいかもしれませんね。
2章 クリスマスリースの歴史

今度はリースの歴史を覗いていきましょう。
意外なことに、リースの始まりは、なんとキリスト教ではありませんでした。
リースの起源は、キリスト教誕生以前の古代ギリシャまでさかのぼります。
当時、詩人や勇者の栄光を讃えるために、月桂樹やオリーブで作った冠が捧げられていました。
今でもオリンピックの聖火ランナーは、オリーブの冠をかぶっていますね。
そのリースをドアに飾ることは、勝利や栄光を示す社会的ステータスだったのです。
その後もリースは、王者の冠となったり、花嫁の装飾品となったり、死者へ手向ける花輪となったり、さまざまな形で歴史に登場します。
いずれも日常ではなく、特別な日の演出として使用されていました。
残念ながら、リースがクリスマスと結びついた詳しい起源はわかっていません。
リース自体の歴史は古いですが、クリスマスの装飾品として使われるようになったのは、近年になってからなのかもしれませんね。
3章 リースを飾る期間

12月になると、街中でクリスマスリースを見かけるようになります。
しかし、11月から飾っているお宅も、年が明けても飾っているお宅も、たまに見かけますよね。
いつからいつまで飾っておくことが正解なのでしょうか。
3-1、キリスト教圏におけるクリスマスシーズン
実は、キリスト教圏でもクリスマスリースを飾る期間は、2通り存在しています。
- アドベントの始まり(11/30にもっとも近い日曜日)から公現日(主に1/6)まで
- アドベントの始まり(11/30にもっとも近い日曜日)から聖燭祭(2/2)まで
見慣れない名前がたくさん出てきて、戸惑ってしまいますよね。
アドベント、公現祭、聖燭祭、この3つの解説をしていきましょう。
・アドベント(降誕節・降臨節)
アドベントとは、ドイツ語でクリスマス前の4週間のこと。
イエス・キリストの降誕を待ち望む期間のことです。
その年の11/30にもっとも近い日曜日からクリスマスイブまでのことを指し、その期間中は日曜日がくる毎に、アドベント・リースという壁にかけないリースに蝋燭を1本ずつ立てていきます。
ラテン語で「到来」を意味する「adventus」を語源としており、11/27~12/3までのいずれかの日に始まります。
・公現祭(エピファニー)
神がイエス・キリストの姿をとって人間の前に姿を現した日と言われています。
教派によって日付が異なりますが、主に1/6を指します。
東ローマ帝国支配域、つまり東方教会ではこの日にキリストの生誕を祝うことが主流であったといいます。
この日までにクリスマスの飾りを片付ける、という人が多いようです。
・聖燭祭(キャンドルマス)
イエスが生後40日後に神殿で清められたことを祝する日です。
2/2のことを指し、この日までクリスマスの飾りを残しておく、という教派もあるようです。
聖母マリアの清めとも呼ばれます。
かつてユダヤ教では「赤子は生まれながらにして罪を背負っている」といわれ、赤子は神殿で清められるものでした。
以上のことから、クリスマスの飾りは11月末~2月頭、節分の時期まで飾ってあってもおかしくない、ということがわかります。
教会などは1月でもクリスマスリースを飾っているところが多いですが、決して片付け忘れているわけではない、ということですね。
とはいえ、日本でここまでしている人はめずらしいですよね。
日本であればたいてい、クリスマスが終わればすぐにお正月の準備に入ります。
クリスマスまでは玄関に飾られていたリースが、翌日にはもうしめ縄に替わっていた、なんてこともよくある話です。
クリスマスリースを飾っておく期間として国内でもっとも一般的なのは、12月に入ってから飾り、28日にお正月飾りを出すまでに片付ける、というものでしょう。
宗教的な意味合いが少ない日本国内においては、好きなときに出して好きなときに片付ける、という認識でも問題なさそうです。
3-2、日本におけるクリスマス
さて、リースを飾る期間ひとつとっても、キリスト教圏と日本国内ではずいぶんと違います。
そもそもクリスマスというものに対する認識自体が、日本はずいぶんと独特なようです。
クリスマスとはキリストの生誕を祝う宗教的な行事なのですが、そう思って祝っている日本人が、はたしてどの程度いるでしょうか。
日本人のなかでキリスト教徒の占める割合が何パーセントだか知っていますか?
答えは0.8%で、明治維新後に全体の1%を超えたことはありません。
そんなキリスト教徒がほとんどいない日本国内における、独特の風習をいくつか書き出してみましょう。
・クリスマスの夜はカップルで過ごす
日本国内では、クリスマスといえばカップルで過ごすことが定番となっています。
クリスマスまでに彼氏を作る!といった特集を組む女性誌もよく見かけますね。
しかし欧米では、クリスマスはキリストに感謝を捧げ、自宅で家族や親戚とパーティーを開くことが普通です。
・ケンタッキー・フライドチキンが飛ぶように売れる
クリスマスといえばケンタッキー、というご家庭も多くあるのではないでしょうか。
事実、日本KFCは12月23日~25日の3日間で、年間売上の1割を売り上げるそうです。
よく言われることですが、クリスマスに普通のチキンを食べるのは日本独特の文化です。
本来は、クリスマスのごちそうといえば七面鳥のローストですね。
1970年代までは七面鳥を買って食べる人たちもそれなりにいたようですが、その時期からKFCの広告宣伝効果が広がり、チキンが定番となったのだといわれています。
国内では七面鳥が珍しく、入手しづらかったことも理由のひとつといえるでしょう。
・クリスマスを祝うわりには休みじゃない
イベントとして定着しているクリスマスですが、クリスマス=休日という企業はほとんどありませんよね。
欧米では、期間はまちまちですが、基本的にクリスマス休暇があります。
キリストに感謝を捧げて家族で過ごすものだ、という共通認識が国単位であるため、そういった制度が存在するのですね。
これも、クリスマスを宗教的な行事として祝っているのか、単なるイベントとして捉えているのか、というひとつの指標として挙げることができそうです。
このような日本人独特のクリスマスは、外国の方からすると奇異に映るようです。
日本人にはさまざまな宗教観が混在し、そのうえ祭りを尊ぶ文化があります。そのため、異国の祝祭も楽しいイベントとして受け入れてしまうのでしょう。
日本はたびたび、無宗教の国だといわれます。
仏教やキリスト教、その他にもたくさんの宗教が日本には存在しますが、どんな宗教も海外から入ってきたものは時間をかけて日本独自のものに変化していきます。
日本独特の文化受容はたびたび論じられているので、興味のある人はインターネット上にある論文を探して読んでみるのもいいでしょう。
4章 クリスマスリースを飾ろう

今度は実際にクリスマスリースを飾ってみましょう。
4-1、飾る場所
クリスマスリースは玄関に飾ることが一般的ですが、特に決まりがあるわけではありません。
マンションや賃貸などで玄関のドアには飾れない、という人もいるでしょう。ドアの外側は共用部分である場合が多く、飾り付けなどは禁止されていることもあります。
玄関に拘ることなく、自分の家の好きなところに飾るといいでしょう。
飲食店やショッピングセンターでも、インテリアとして自由な位置に飾られていますよね。
「素敵だな」と思ったディスプレイをしている店舗をお手本にしてみるのもいいでしょう。
4-2、飾る方法
飾る場所を決めたあとに、困るのは飾る方法です。
ドアや壁にフックをつけて吊るすのが基本ですが、壁に穴をあけたくない、粘着テープをつけたくない、という人も多いと思います。
そんな人たちのために、いくつか飾る場所を傷つけない方法をご紹介します。
・置く
「いきなりそれか!」と言われてしまいそうですが、いちばん簡単な方法は、吊るさないで置いてしまうことです。
飾り棚に入れてみたり、カウンターテーブルに立てかけてみたり、ピアノの上に置いてみたり。
シンプルなワンルームなら、直接床に置いてしまっても意外におしゃれだったりしますよ。
・イーゼルを使う
画家が絵を描くときに使うイーゼルは、小型のものだとインテリアの簡単な台座として使うことができます。
厚みの少ないものなら直接イーゼルの上に置いても安定しますし、バランスが悪い場合は針金などを使って固定しましょう。
イーゼルは画材店やインターネット、100円ショップなどで購入できます。
・ドアフックを使う
ドアの上部に差し込んで使うフックを使えば、どこにも傷をつけずにリースを吊るすことができます。
ドアフックは100円ショップでも購入できるので、非常におすすめですよ。
・マグネットフックを使う
取り付ける場所が金属なら、強力なマグネットフックを使うのもひとつの手です。
多少の衝撃にはばびくともしませんし、少し場所は選びますが、有用なアイテムです。
マンションのドアなども、マグネットフックが使えるケースが多いようです。
・跡のつかないピンフックを使う
賃貸の壁紙に刺しても大丈夫、という極細ピンがインターネットで販売されています。
耐荷重も1kgから5kgほどまでの商品が多いので、リースなら十分にかけることができるでしょう。
本当に跡がつかないかどうか、目立たないところで試すことを忘れないでくださいね。
5章 まとめ

リースにまつわるさまざま疑問を消化してきましたが、いかがでしたか?
すっきりできたでしょうか。
キリスト教が発祥ではなかったり、節分の時期まで飾ってあっても間違いではなかったりと、意外な事実がたくさん出てきました。
深い意味の込められたクリスマスリースを、ぜひご自宅に飾ってみてください。
きっとあなたを守って、素敵なクリスマスにしてくれますよ。
提供・はな物語
こちらの記事は、プリザーブドフラワー専門店・はな物語の提供でお送りしました。
記事の内容は参考になりましたか?
クリスマスリースの由来を知る一助になれば幸いです。
もしリースに飾る花をお探しでしたら、手間が少なく、美しい姿を長くとどめるプリザーブドフラワーもおすすめです。
ぜひ、サイトもご覧になってみてくださいね。